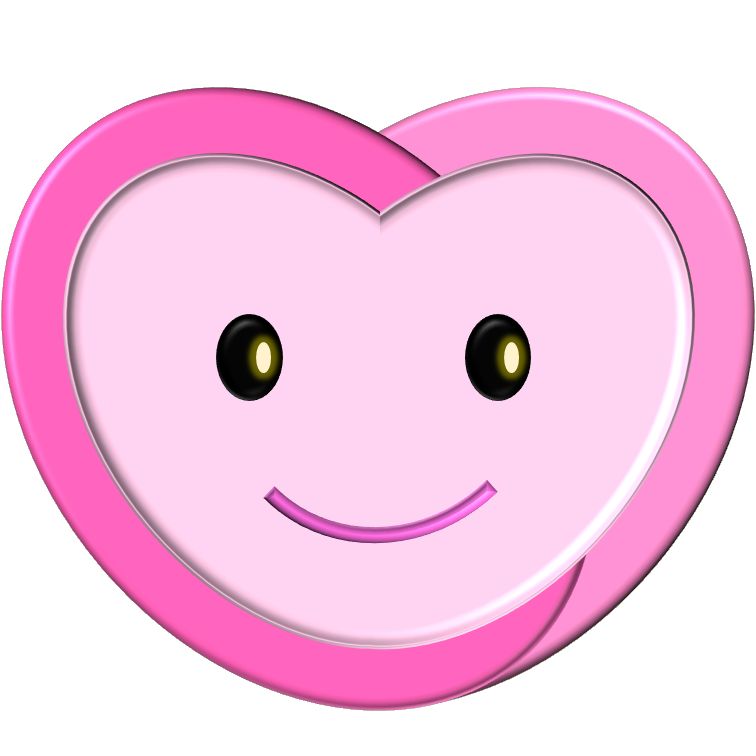あなたは、今、お悩みやストレスを抱え苦しんでいませんか?
あなたが今感じている世界は「あなたのすべてではありません」
あなたが今感じている世界は「あなたのすべてではありません」

夕食の買い物に行き、「今日は何を作ろうか?」考えている自分・・・

読書に没頭し、ファンタジーな世界に身を投じている自分・・・

好きな物を食べ、至福の瞬間に浸っている自分・・・

ただただ、家で寝っ転がり、ひたすら自分を癒している自分・・・

友人との楽しい会話に夢中になり、嫌なことをすっかり忘れてしまっている自分・・・

あなたは、それらの自分の存在に気づいていますか?
あなたは、それらの自分を「かけがえのない大切な自分」だと認めてあげていますか?
あなたは、それらの自分を「かけがえのない大切な自分」だと認めてあげていますか?

あなたが、もし、「自分の中にいるいくつもの自分の存在」を認めてあげたら、どういう【行動】を起こしてみるか考えてみましょう

もし、なんだか面倒になり、やめてしまったカメラを再び始めてみたら、今この瞬間の幸せを感じられるのかもしれない・・・

何事にも熱中するあなたが、もし、未来に向け、資格取得の勉強を始めたら、未来に希望を持ち、前向きになれるのかもしれない・・・

好奇心旺盛なあなたが、もし、勇気を出して一人でおしゃれなカフェに行ってみたら、ゆっくりと自分自身を見つめなおすことができるのかもしれない・・・

楽しいことが好きなあなたが、もし、友達と一緒に旅行
に行ったら、それが心の支えになるのかもしれない・・・
に行ったら、それが心の支えになるのかもしれない・・・

もし、忙しい中、時間を作り、大好きな彼氏に思い切って悩みを打ち明けたら、今まで悩んでたことがどこかに飛んで行ってしまうのかもしれない・・・

【行動】を起こして、『無意識のプログラム』を書き換えていく

柔軟な『モード切替』ができるようになる心理カウンセリング

カウンセリング
こころの相談所
こころの相談所